「世界一即戦力な男」に見る引きこもり脱出の糸口
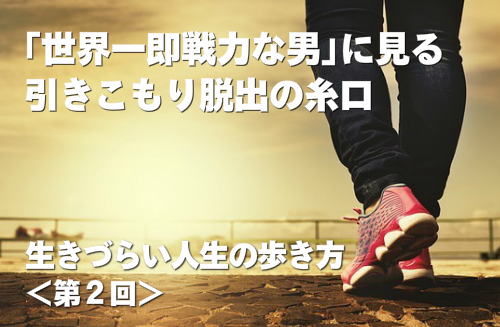
生きづらい人生の歩き方
第2回
「世界一即戦力な男」に見る引きこもり脱出の糸口
┃引きこもりにもさまざまな「タイプ」がある
先日、「世界一即戦力な男」(菊池良著 フォレスト出版)という本を読みました。
高校を中退した引きこもり男子が、さまざまな悪戦苦闘をつづけ、ついには「世界一即戦力な男」という引きこもりの自分自身をアピールする「逆就活サイト」を公開。
プランナーとしてIT企業に就職を果たすという、著者の実際の経験を語った啓発書です。
この本には、
「引きこもり脱出の糸口」
が示されています。
私は、カウンセラーという仕事をとおして、引きこもりと呼ばれる人たちと深く接してきました。
また自身も、中年になってから長く引きこもっていた時代があります。
引きこもりと呼ばれる人が、実際に社会から身を遠ざけてしまう理由は、本当に多様で複雑です。
さまざまなタイプの「引きこもり」があるのです。
しかし、それを突き詰めて探っていくと、大きく二つのタイプに分けられると私は考えています。
実は、そのタイプによって「引きこもりの脱け出し方」が明確に違ってくるのです。
「引きこもり」の二つのタイプとは、
「さらけ出せる」か「さらけ出せない」か
です。
┃プライドが引きこもりを正当化させる
「世界一即戦力な男」の著者である菊池さんは、悶絶しながらも、少しずつ自分を「さらけ出す」ことを実践していった。
現代ならではのツールやコミュニティの選択肢の多さを活かし、その中から「さらけ出す」場を自ら選び、飛び込んでいった。
とてつもなく苦しんだけど、「さらけ出す」ことができる人だったと言えるでしょう。
しかし、引きこもりをつづける人の中には、「さらけ出せない」人が多くいます。
これは、引きこもっている本人がもっている「プライド」を、守ろうとするか、捨てられるかという問題に言いかえられるかもしれません。
引きこもりになる人は、自分には社会で生きていける能力がないと感じ、全方位的に劣等感を覚えていることがとても多いものです。
その感じ方を、時間をかけてでも素直に受け入れられる人は、やがて「プライド」を捨てて劣等感を克服し、自分を「さらけ出す」ことで引きこもりから脱け出していきます。
しかし、たいていの人の場合は、その劣等感を認めつつも、
「私には本当は能力があるのだが、それを受け入れられない社会が悪い」
といった考えや、
「私のような繊細な感性は、雑な感性の社会には理解できない」
といった考えで上書きして、自分の「プライド」を守ろうとします。
また哲学書などに影響を受けて、
「私のような真実を知る人間は社会ではやっていけない。適応しようとすればできるが、社会にはそこまでの価値がない」
といった論理で、自分の「プライド」を守ろうとすることもあります。
つまり、自分を社会より「上」の存在に置き、社会を見下すことによってなんとか「プライド」を保ち、引きこもりを正当化しようとするわけです。
引きこもりの中で、「生きづらい」とまで感じている人は、このパターンに当てはまることがとても多いと言えるでしょう。
こうなると、「さらけ出す」ことはとてもハードルが高くなります。
なぜなら、他者から評価を受けることが、心の底から恐ろしくなってしまうからです。
もし自分を「さらけ出す」ことで社会の評価を受ければ、自分で自分につけた「高評価」が簡単に覆されてしまう可能性があります。
自分には特別な能力はなく、繊細でもなく甘えているだけで、真実を知っているわけでもない。
そんな「単なる社会不適応者」だという一方的な評価が、真っ向から容赦なくくだされてしまうことになりかねません。
そうなれば、社会の方が無能で間違っているという論理が通用しなくなる。
引きこもりを正当化できなくなる。
ましてや自分が見下していた社会の側から、批判されて拒絶されるなんて…。
それはいじめっ子が、いつもいじめていた相手に反撃され殴り倒されて、みんなの目の前でボコボコにされてしまうようなものかもしれません。
そんな恥ずかしく恐ろしい現実には、とてもではないが耐えられない。
だから、「さらけ出す」ことはどうしても避けねばならない。
そうして引きこもりが長引いていくことが多いのです。
さらに、年齢が高くなればなるほど、根拠のない「プライド」が大きくなってしまい、問題は厄介になっていきます。
┃「さらけだす」よりも大切なこと
そこで、よくある引きこもり解決案として、
「だから、あなたもさらけ出して生きていきましょう!」
という「オチ」をよく見かけます。
ただ、そのアドバイスは安易に過ぎるでしょう。
肥大してしまった「プライド」は、引きこもっている人からすれば、まさに命綱。
そうかんたんに手放せるものではありません。
カウンセリングの場でも、このようなご相談をよくいただきます。
誰もが菊池さんのように、勇敢に「さらけ出す」ことができるわけではないのです。
では、どうしたらいいのでしょうか?
それは、無理に「さらけ出す」ことにこだわらなくていい、ということ。
できるだけさらけ出さずに、どすれば自立できるかを「本気」で考えてみてもいいのです。
「そんな都合のいい話なんてある…?」
そう思う人もいるかもしれません。
でも、そこまで手放せない「プライド」なら、無理に捨てなくていい。
その上で、どうすればいいのかを真剣に考え、それを実行していけばいいのです。
今まで「さらけ出す」ためには行動ができなかった。
でも、大切な「プライド」を守るためになら行動できるかもしれません。
そこにこそ「本気」になる。
そんな生き方だってあるのです。
「 世界一即戦力な男」の中にも、ブログやツイッターなど、たった10年前にはろくに使われていなかったツールが活躍しています。
さらに、さまざまな趣向のコミュニティが社会的に認知されているのを知ることもできます。
引きこもりの脱け出し方も今までの時代とは違ってきており、人によってさまざまなのです。
つまり、見習うのは菊池さんの「さらけ出す」姿勢でない。
菊池さんが「自分なりの方法」で脱け出していった姿勢。
そこにこそ、本当の「引きこもりから脱け出す糸口」が示されている。
私は、そう思います。
私たちは一人では生きてはいけません。
というか、生まれてくることすらできません。
いついかなるときも「社会」の一員です。
だからと言って、常に「社会」の求める型にハマる必要はない。
自分なりのやり方を「社会」に提示してみる。
そうして「社会」は形を変えていくのです。
でなければ、今でも石器時代のままのはずなのですから。
Brain with Soul代表
生きづらさ専門カウンセラー
しのぶ かつのり(信夫克紀)

菊池良「世界一即戦力な男」フォレスト出版
生きづらい人生の歩き方 <目次>
1.生きづらい人がAI時代に生き残れる仕事とは?
2.「世界一即戦力な男」に見る引きこもり脱出の糸口
3.生きづらい人向け「ビジネスの成功法則」
4.あなたは「善人」ですか「悪人」ですか?
5.お金は好きですか?-生きづらい人が陥るお金のジレンマ
6.「お金もうけ」にとらわれなくなる話
7.生きづらい人は「リア充」より「ジツ充」を目指そう
8.我慢してるのに自分勝手と言われる
9.生きづらさの正体
10.死んでも世界はつづくのか?
11.実存を充実させる生き方
12.他人の目が気になる人へ
13.「ジツ充」の極め方
14.不安の上手な対処法
15.変えられること、変えられないこと
16.「変えられること」の見つけ方
17.感情に飲み込まれない方法
18.自分と同じ症状の人が見当たらない
19.人生を変える方法
20.人生が変わる瞬間に必ず起こる問題
21.「心の空間」を生きる
22.話が噛み合わないと感じるなら
23.人生に疲れ果てたとき
24.「自分らしさ」とは何か?
25.AIと張り合うくらいなら
26.ジツ充とジコチュウの違い
27.社会に絶望している人へ
28.ネガティブ思考を変える適切な方法
29.生きづらい人は仕事を「三つ」もとう
30.心の健康法の効果が出ない理由
31.ベーシックインカムで将来も安心?
32.「悩み解決書」で悩みが解決しない理由
33.生きづらさを癒す一つの方法
34.もっとクヨクヨ考えよう
35.仕事を三つもつ理由
36.好きなことを仕事にする…?
37.苦しみの活かし方
38.向かい風を追い風にする生き方
39.行動力を身につける方法
40.お金との上手なつき合い方
41.自己洗脳と自己欺瞞
42.人並みという幻想
43.元気がないと幸せになれないのか?
44.「社会の常識」に振りまわされない
45.気が休まらない…
46.綺麗事に気づいてしまう人
47.生きづらい人が起業を成功させられる理由
48.そんなかんたんな話じゃない
49.人に気をつかい過ぎて疲れしまう
50.悩み過ぎて体がガチガチ
51.正解なんてない
52.心に余裕がない
53.誰に相談したらいいのかわからない
54.やる気はどこから湧いてくる?
55.人と対立してしまう
56.許すか、許さないか
57.生き方を決める
58.好きなこと探しの迷宮
59.生きづらさは誰のせい?
60.集中しすぎてしまう
61.家にも世の中にも居場所がないときの解決法
62.不用意に交友関係を増やそうとしない
63.自分を最強の味方にする方法
64.世間のしがらみから脱け出したい
65.あと一歩が踏み出せない
66.なぜメンタルが弱いのだろう…?
67.生きづらい人が「苦手」を克服する方法
68.心配ごとが頭から離れない
69.認められたいのに認めてもらえない
70.引きこもりは「悪いこと」なのか?
71.楽に生きたい
72.失言が多いので減らしたい
73.誰も心配してくれない
74.お金の上手な使い方
75.やる気が出ないのはなぜなのか?
76.深く悩んでいる人の方が「えらい」のか?
77.生きづらい人が幸せになりたいなら
78.この人と結婚していいのか?
79.心が敏感な人向けの対処法から抜け落ちている視点
80.人生を変えられる人と、変えられない人の違い
81.親が嫌いな自分はおかしいのか?
82.著名人と自分を比べてしまう
83.自分を信じられない
84.上司や部下に言うことを聞いてもらえない
85.劣等感は克服も解消もしなくていい
86.ポジティブシンキングがうまくできない
87.結果だけで判断される社会
88.「自分がされたら嫌ことは他人にしてはいけない」の嘘
89.「性格が悪い」と言われてしまう
90.「ありのままの自分」というやっかいな問題
91.「お金」以外に8つの基準をもとう
92.どうしてこんなにつらいのに誰にも伝わらないのだろう?
93.仕事が恐い、職場が恐い - その恐怖の正体と解決策
94.「恩知らずな人」を許せない
95.他人を不愉快にさせてしまう
96.「等身大の自分」という言葉にひそむ罠
97.有効な「貯金」の仕方を身に着けよう
98.「なぜ怒っているのかわからない」と言われてしまう
99.頑張っているのに結果が出ない・・・
100.自分を「弱い」と感じている人へ
101.集団になじめないなら「思いどおり」にやろう
102.無駄に苦しんできただけだった
103.お金の不安をなくす方法
104.私の「すべて」をわかってもらいたい - わかってもらいたい症候群
105.なぜ苦しみを「克服」できないのか?
106.生きづらいなら「心地よい人生」を目指そう
107.生きづらい人は「扁桃体をいたわる生き方」を身に着けよう!
108.生きづらい人が自由になれる「メタ思考」とは?
109.世間との「ほどよい距離」の取り方とは?
110.たんたんと生きる
111.生きづらい人が目標を達成できない本当の理由
112.三理一体の法則がうまくいかない人の共通点とは?
113.カタルシスが生きづらさ脱出の「起爆剤」になる理由
114.「生きづらさ克服」の気力を失いそうなあなたへ
115.「仕事に行きたくない、家にいたい」当事者の声と具体的な対処法
116. 気が弱い人が人生を変える極意
117.消えない恨みへの「レベル別」対処法
118.生きづらさをこじらせる「完全な被害者バイアス」とは?
119.生きづらいなら「役割」を果たし人生を落ち着かせよう
120.生きづらい人にもっとも大切な支援
121.生きづらい人は「意志が弱い」のか?
122.自分軸よりも大切なもの -「実存軸」で生きよう
123.人の言葉に傷つきやすい人が知ると楽になる二つの事実
124.メタ思考力を鍛えたいなら「バカ」や「アホ」ともつき合おう
125.生きづらさの「原因」を安易に特定するネット記事が多すぎる
126.「誰でもHSP症候群」にかかった日本
127.「結論だけ欲しがる社会」に踊れされるな
128.生きづらい人は「ギバー」を目指さなくていい
129.「一人で生きていく」と決めた生きづらい人に必要な覚悟
130.マイノリティは、なぜ生きづらいのか?
131.生きづらい人の「意識」の上手な活かし方
132.もんもん耐性、それは自分の「本質」と向き合える力
133.生きづらい人はAIと仲良くなれる - 関係性のシンギュラリティ
134.「メンタルが強い人」のアドバイスを真に受けない
135.雑談力は必要か?雑談できないあなたへ
136.嫉妬しやすい人が「嫉妬しない人」になりたいなら
137.お金に振り回されなくなる「二つの力」
138.日本社会で生きづらい人が苦しんでいる本当の理由
139.自分は本当に「生きづらい」のだろうか?
140.生きづらい人はコミュニケーションが得意という事実
141.内にこもりたいとき、あなたはどうしていますか?
142.「憧れの人」を目指すな - ビジネスの成功者に憧れる生きづらい人へ
143.私には不満がない
144.「無駄にプライドが高い人」が好きだ
145.その他大勢になるな、唯一無二のままであれ。
146.「生きる意味」が見つからない、生きづらい人へ
147.「異物」として生きて
おかげ様でコラム数500本突破!

 目次はコチラ
目次はコチラ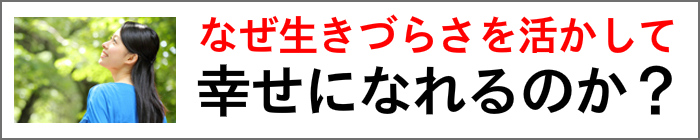
 生きづらい人向け「ビジネスの成功法則」
生きづらい人向け「ビジネスの成功法則」 生きづらい人がAI時代に生き残れる仕事と...
生きづらい人がAI時代に生き残れる仕事と... 「読むと心が強くなるコラム」一覧
「読むと心が強くなるコラム」一覧