すぐに役立つセロトニン基礎知識(4)
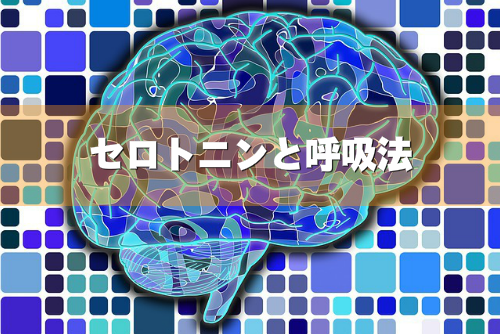
セロトニンと呼吸法
1.呼吸法は『リズム運動』
呼吸法によって脳内のセロトニン量を増やせることが、研究結果からもあきらかになっています。
この「セロトニンを増やす呼吸法」とは、どんなものなのでしょうか?
それは、呼吸を「リズム運動」としておこなうのです。
脳内のセロトニンがリズム運動によっても増えることは、先述したとおりです。
このリズム運動は、5分以上の疲れない程度のリズミカルな運動である必要があります。
さらに、リズム運動に集中する、つまり「意識的にリズム運動する」ことが重要になってきます。
その条件に最適なのが、座禅などでおこなわれる『呼吸法』なのです。
といっても、ただ普段どおりに息を吸ったり吐いたりしていてもセロトニンを増やすことはできないと考えられています。
『意識的なリズム運動』として、呼吸をおこなう必要があるのです。
その呼吸法を、
『腹筋呼吸』
といいます。
(腹式呼吸ではないのでご注意ください)
この『腹筋呼吸』とは、いったいなんでしょうか?
2.腹筋呼吸法とは?
まず、くり返しとなりますが、『腹筋呼吸』(ふっきんこきゅう)は、「腹式呼吸法」(ふくしきこきゅう)とは別のものなのでご注意ください。
『腹筋呼吸法』とは、文字通り腹筋を使っておこなう呼吸のことです。
私たちは普段、腹筋ではなく、横隔膜を使った 「横隔膜呼吸」 をしています。
これは、呼吸していない自然な状態をスタート地点として、息を「吸う」ところから始める呼吸法です。
そして、自然と息を「吐き」、また自然なスタート地点へと戻ります。
この時、胸がふくらむ呼吸法を「胸式呼吸法」(きょうしきこきゅう法)、
腹がふくらむ呼吸法を「腹式呼吸法」(ふくしきこきゅう法)と呼びます。
これら横隔膜呼吸は、私たちが意識することなく自動的におこなっています。
しかし、脳内のセロトニンを増やすためには『意識的におこなうリズム運動』が必要だと、ご説明しました。
そこで『腹筋呼吸法』(ふっきんこきゅう法)をおこなう必要があるのです。
『腹筋呼吸法』は、強く意識しておこなう呼吸法です。
では、横隔膜呼吸と『腹筋呼吸法』では、何が違うのでしょうか。
それは息を「吐く」ところからはじめるという点です。
つまり『腹筋呼吸』は、横隔膜呼吸とは真逆に、呼吸していない自然な状態をスタート地点として、息を「吐く」ところから呼吸を始めるのです。
スタート地点から、息を「吐く」ためには、お腹を強くへこませなければなりません。
つまり、腹筋を強く縮めなければなりません。
この運動が、『意識的なリズム運動』になり、セロトニンを増やす効果があるのです。
息を吐ききれば、自然とお腹はもとにもどり、息が吸い込まれてきます。
これが『腹筋呼吸法』です。
3.息を吐く時間の方を長くする
『腹筋呼吸法』を効果的におこなうためには、以下の3つのポイントをおさえる必要があります。
1.息を吐く時間の方を長くする
2.息を吐ききる
3.半目でおこなう
まずは1つ目のポイント、「息を吐く時間の方を長くする」について、ご説明いたします。
吐く時間の方を長くする。
これは、人間の自然な生理活動の原則にしたがいましょうということなんです。
人間の呼吸は、「吸う」時間よりも、「吐く」時間の方が1.5倍から2倍長いのが自然な状態です。
比率を変えると、過呼吸や酸欠になりかねません。
あらためて後ほどご説明いたしますが、脳内のセロトニンを増やすためには、『腹筋呼吸法』を最低でも5分間、長ければ20分~30分程度おこなう必要があります。
無理に比率を変えてしまうと、呼吸が苦しくなり続けることができなくなってしまうでしょう。
また、よく「10秒吐いて5秒吸う」など、吐くのも吸うのも数を完全に決めておこなう場合があります。
これも長時間やり続けると、どこかで苦しくなってしまいます。
時間の経過とともに送られてくる体からのサインにしたがって無理せず楽に続けられる長さで呼吸をするようにしましょう。
4.息を吐ききる
次に『腹筋呼吸法』の2つめのポイント「息を吐ききる」についてご説明いたします。
『腹筋呼吸法』は、腹筋をしぼって差異母まで『息を吐ききる』ことが重要になります。
『腹筋呼吸法』は、脳内のセロトニンを増やすための意識的なリズム運動です。
つまり、自然な呼吸活動ではなく「腹筋運動」なんです。
ニュートラルな呼吸のスタート地点から、腹筋を絞って吐いて吐いて吐ききる。
こうすることで、呼吸中枢からの信号でおこなう自然な呼吸活動ではなく、大脳皮質からの信号でおこなう意識的なリズム運動になるのです。
そのためには、吐いて吐いて吐ききる。
かといって、無理に吐きすぎますと、酸欠になってしまいますのでご注意くださいね。
また、疲れてしまっては、呼吸法を続けることができなくなってしまいますよね。
先述したように、「吸う」時間に対して、「吐く」時間が1,5倍から2倍になるように、体のサインにしたがって調整し、自分をいたわりながら続けましょう。
『リズム運動』というと、小気味よく、サッサッサッとおこなう運動をイメージすることが多いかと思います。
しかし、『腹筋呼吸法』は、そんなにあわただしく行なう必要はありません。
ゆっくり吐ききって、ゆっくり吸っても十分に効果があるんです。
ゆっくりであっても、集中して動く運動であれば意識的なリズム運動になるのです。
吐いて吐いて吐ききれば、吸う動作は自然と行なわれますので、特に意識する必要はありません。
5分以上続けるとセロトニン神経が活性してきます。
力強く吐ききりすぎて、5分ももたないということのないよう、無理せず心地よい範囲でおこなってくださいね。
5.半目でおこなう
腹筋呼吸法の3つ目のポイントは、<半目でおこなう>ことです。
半目、つまり目を半分開いた状態です。
半目でおこなう理由は「リラックスしすぎないため、そして「集中力を高めるため」です。
呼吸法というと、「リラックスして安らぐためのもの」といったリラクゼーションのようなイメージを持つ方が多くいらっしゃいます。
もちろんそれも正しいのですが、『腹筋呼吸法』にかぎっては、脳のセロトニンを増やすための、
「腹筋運動」
と考えていただくのが解りやすいかもしれません。
ウォーキングや軽いジョギングなど、心地よい負荷をかけた運動なのです。
実践後のご感想も、「リラックスできて心身が休まった」という方よりも、「頭がシャキッとして爽快な気分になった」という方がほとんどです。
『腹筋呼吸法』は、わざわざ着替える必要もなく室内で手軽に座っておこなえるのが大きな利点です。
ただ手軽に座っておこなえるがゆえに、『目を閉じておこなう』と、慣れないうちはリラックスしすぎてしまい、時には眠ってしまうのです。
もちろんこれでは、セロトニンを増やす方法になりません。
「リラックス」と「爽快」という感覚の違いには実は脳波に大きく違いが現れます。
私たちは目を閉じると、「リラックス」している時の脳波であるα波(アルファ波)が発生します。
それに対して、『腹筋呼吸法』を5分ほど続けると、『速いα波』という脳波が発生します。
この『速いα波』が出ると、「リラックス」ではなく「爽快」な気分になると考えられているのです。
目を閉じたまま『腹筋呼吸法』を続けていると7分頃までは「リラックス」のα波が出てきてしまいます。
このため、慣れないうちは眠ってしまうのではないかと考えられます。
かといって
「視界全開!」
と意気込んで『腹筋呼吸法』をおこなっても、やはり慣れないうちは集中できずに、効果的なトレーニングにはなりません。
そこで、
「半目でおこなう」
わけです。
半目でおこなえば、集中しながら「リラックス」のα波もおさえることができ一石二鳥というわけなんです。
ただし慣れないうちは、『半目』でも眠ってしまう場合があります。
これを避けるために、集中力を保ちながら腹筋呼吸をおこなうために私lが開発した呼吸法が「かぐら呼吸法」です。
かぐら呼吸法の研究結果についてついて詳しくは、下記の記事をご参照ください。
<参考記事>
【論文】セロトニン活性を成功させる三理一体の法則 - うつ病、PTSD、ボタノフォビア諸症状緩和の考察
6.腹筋呼吸法と姿勢
腹筋呼吸法を指導させていただくと、姿勢について質問をいただくことが多くあります。
精神の鍛錬のために、座禅や瞑想などに取り組んでおられる方は、特に姿勢が気になることが多いようです。
確かに座禅などでは、姿勢などもしっかり指導を受けますよね。
でも、『腹筋呼吸法』では、特に姿勢を気にする必要はありません。
立っていても、座っていても、あぐらをかいても、椅子に腰掛けていても、脳内の セロトニンを増やす方法としては問題ないと言われています。
なぜなら重要なのは、 意識的なリズム運動の方、つまり呼吸運動の方だからです。
また、「 セロトニンを増やす5つのメリット」でもご紹介したように、セロトニン神経が鍛えられてくると、抗重力筋という姿勢を正す筋肉を刺激してくれます。
無理に姿勢を良くしようとしなくても、自然と姿勢が良くなってきてくれるということです。
まずは楽な姿勢で、『腹筋呼吸法』に取り組んでみてください。
私もそうでしたが、回数を重ねるごとに、自分が『腹筋呼吸法』をしやすい姿勢が見つかります。
慣れるまでは、呼吸運動の方に意識を集中させるといいでしょう。

有田秀穂「セロトニン欠乏脳」NHK出版
信夫克紀「セロトニン活性を成功させる三理一体の法則 - うつ病、PTSD、ボタノフォビア諸症状緩和の考察」2014
おかげ様でコラム数500本突破!

 「読むと心が強くなるコラム」一覧
「読むと心が強くなるコラム」一覧