自分の悩みが伝わらない
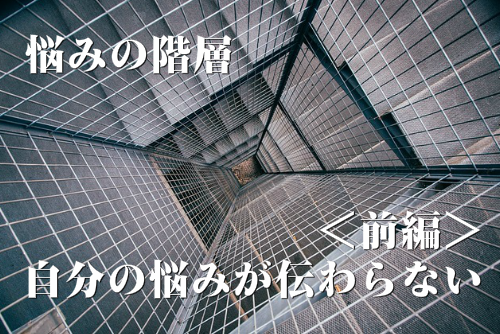
悩みの階層
<前編>
自分の悩みが伝わらない
┃なにかがズレている わかってもらえた気がしない
あなたは、このような感覚をもったことはありませんか?
たとえば「悩み解決書」や「心理学の本」を読んだときに、
「なにかが違う」
「私には当てはまらない」
と感じる。
また、セミナーや自助グループに参加したときに、
「私の悩みだけ異質な気がする」
「みんなの悩みと私の悩みは、なにかがズレている」
と感じる。
つまりどの事例も、どの解決策も、どの人の体験談も、どのアドバイスも、自分にはピタリと当てはまらない。
そんな感覚です。
そこで、専門家である精神科医や心理カウンセラーに相談しても、
「なるほど」
「そうなんですね」
「では、こうしてみましょう」
と、軽く流されてしまう。
懸命に自分の苦しみを伝えるけど、まったく伝わった感じがしない。
わかってもらえた気が、ぜんぜんしない。
じっさいに診断やアドバイスを受けても、自分の悩みの本質とあきらかにズレている。
しかし、そのズレがいったいなんなのか、自分にもわからない。
そして、一人もんもんと孤独を抱えて苦悩することになる…。
もしあなたが、このような体験をしてきたのなら。
それは、
「悩みの階層」
がズレているためかもしれません。
あなたの「悩みの階層」は深い。
だから、どうしても根本的な「ズレ」を感じてしまう。
周囲の人と「悩みの階層」が違うために、どうしても話しが通じないのです。
┃悩みには「階層」がある
悩みには、浅いものから、深いものまで、さまざまな階層があります。
それを世間では「悩み」という言葉でひとくくりにしているため、話が噛み合わない。
あなたの生きづらさや苦しみが理解されず、切実さが伝わらないのです。
「でも、ちゃんと自分の悩みに合った分類の本を読んだり、そういうセミナーを受けたり専門家を選んでます」
たしかに、そうですよね。
メンタルケア業界には、悩みにおけるたいへん多くの分類があります。
しかし、悩みを深さでとらえる「悩みの階層」という分類は存在していないのではないでしょうか。
現在おこなわれている分類は、「症状、原因、手法」にもとづいた分類ばかりです。
たとえば、アダルトチルドレン、燃え尽き症候群、HSP、モラハラ、パワハラ、DV、実存的、哲学的、自己超越的、スピリチュアル、PTSD、うつ病、適応障害、発達障害、社会不安障害、心理カウンセリング、精神分析、認知行動療法、マインドフルネス瞑想、などなど…。
たしかに、これらの分類は重要で、じっさいに役立てられている貴重なもの。
たいへん多くの英知が詰まっています。
ただ、言うなればこれは「平面」での分類だと言えるでしょう。
ここには「悩みの階層」という、
「垂直方向」
に分類する感覚がスッポリ抜け落ちています。
つまり、「深さ」という感覚が存在していないのです。
いったいなぜでしょうか?
それは、心理療法家や医師、カウンセラー、研究者といった「使う側」の視点によって解決策が考えられてきたためではないでしょうか。
つまり、現在取り入れられている「平面」の分類は、「使う側」の視点であって、じっさいに悩んでいる人や苦しんでいる人の視点ではない…。
カウンセラーである私自身も、そう認めざるをえないのです。
私は、子供の頃から長いあいだ生きづらさを抱えて生きてきました。
本当に苦しんできました。
誰かに相談しても話が通じませんでした。
そして今では、人様のお悩みをうかがう生きづらさ専門カウンセラーという仕事をさせていただいています。
その両方の経験のなかで、切実に感じていることがあります。
それは、現在のメンタルケア業界が、苦しんでいる人の視点から悩みを見ていないのではないかということです。
もちろん一人ひとりの専門家は、真剣に相談者と向き合っておられるでしょう。
しかし、業界全体という見方をすると、その土台となっている「分類」が「苦しんでいる側」に立っているとは言いがたい。
「使う側」の都合でできあがっている。
それが「メンタルケア業界の現実」だと感じざるをえないのです。
だから私はここで、「悩みの階層」という存在についてあなたに伝えたいと思いました。
なぜなら「悩みの階層」こそが、人から理解を得られない悩みをもつあなたに、どうしても必要な視点だからです。
┃悩みの階層が「深い」とはどういうことか?
ここであらかじめ述べておきたいことがあります。
ご懸命なあなたならすでにおわかりのことと思いますが、「悩みの階層」が浅いから苦しくないとか、価値が低いということではありません。
そして、当然「悩みの階層」が深いから高尚だということでもありません。
あくまでも「階層」が違うだけということです。
では、階層の「浅い」「深い」とは、いったいなにを示しているのでしょうか?
それは、「わかりにくさ」です。
浅い悩みほど、他人から見ても「わかりやすい」。
深い悩みほど、他人から見ても「わかりにくい」。
それどころか、自分から見ても「わかりにくい」のです。
ですので、よく深い悩みの代名詞のように言われる「哲学的な悩み」だからといって、いちがいに「悩みの階層」が深いわけではありません。
哲学的な悩みでも、階層がそれほど深くない悩みはたくさんあります。
たとえば、「なぜ生きるのか?」という悩み。
もちろん答えはかんたんに出せませんが、このような題目自体は、学校で授業の題材に取り上げられることもあります。
過去から現在にかけて多くの書物も残されています。
高校生ともなれば誰かと共有したり、議論したことのある人もいるでしょう。
つまり、悩みの題材そのものは、共有や議論が成り立つ「わかりやすい」悩みなのです。
答えを出すのが難しかったり、論理的に考えることが難しい悩みだから「深い」のではありません。
表面的な問いの難しさが「悩みの階層」を決めるのではない。
あくまでも、どれだけ「わかりにくいか」が階層を決めるのです。
だから、「なぜ生きるのか?」という議論をしているなかでも、「私だけ、みんなと別のことについて語っている気がする…」と感じるならば。
その人のもつ悩みは、深いのです。
また、アダルトチルドレンであることについて専門家からアドバイスをもらっても、「どうしても論点がズレている気がする…」と感じるなら。
その人のもつ悩みは、深いのです。
そして、どれだけモラハラの本を読んでも、「どこか私には当てはまらない気がする…」と感じるなら。
その人のもつ悩みは、深いのです。
もしあなたの悩みが、人に理解してもらえずにいるのなら。
あなたの「悩みの階層」は、深いのです。
次回は、その「悩みの階層」がどのように決まっていくのかを、詳しく見ていきたいと思います。
Brain with Soul代表
生きづらさ専門カウンセラー
しのぶ かつのり
おかげ様でコラム数500本突破!

 目次はコチラ
目次はコチラ
 悩みがわかりにくくなる仕組み
悩みがわかりにくくなる仕組み 目次
目次 「読むと心が強くなるコラム」一覧
「読むと心が強くなるコラム」一覧