超数派という新しい生き方
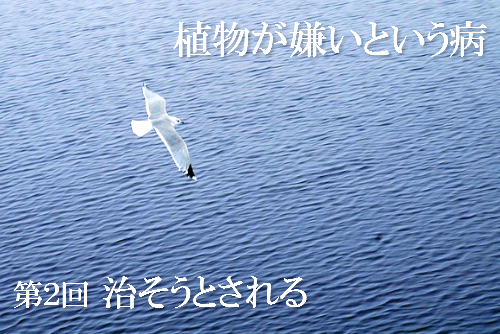
植物が嫌いという病
第2回
治そうとされる
今回は、私が「植物嫌悪症」と(しかたなく自分で)名づけた、社会的には存在していないことになっている「病気」が、いったいどのようなものなのかということについてお話ししたいと思います。
またそれと同時に、植物嫌悪症である私がよく遭遇する、
「治そうとされる」
という問題についてご紹介してみよう(愚痴を言ってみよう)と思います。
前回も述べたとおり、私はいわゆるボタノフォビアや植物恐怖症と言われる人たちと少し違って、植物に恐怖は感じません。
とにかく見た目が気持ち悪くてしかたがなく、見るだけで鳥肌が立つほどおぞましく感じるのです。
想像させて申し訳ないのですが、ゴキ○リが何百匹もうごめいている場面や、大量のう○虫が人間の死体をはい回っている場面を目にしたら、あまりのおぞましさに背筋が寒くなり、目をそらしてしまう人が、日本人には多いと思います。
私にとってはまさに植物がそのように、いえそれ以上に、究極におぞましく見える対象なのです。
そんな私にとって、この世界はたいへん不快な世界です。
たびたび申し訳ないですが、少し想像してみてください。
玄関先やベランダ、広い庭には誰もがたくさんのゴキ○リを飾り、毎朝みんなうれしそうに
ゴキ○リに水をやり、よりたくさんゴキ○リを増やそうとし、レストランの机の上にはゴキ○リが飾られ、テレビをつければセットはゴキ○リで埋め尽くされ、誰もがゴキ○リ柄の服を好んで着て、布団やソファやカーテンはゴキ○リ柄ばかりで、誕生日や記念日のプレゼントにはゴキ○リ束を渡される。
はい、このへんで想像終了。
そのため、私には居ることのできない場所、入ることのできない場所などが多々あり、行動もかなり制限され、同行や同席している方々にご面倒をかけることも多々あります。
すると、どうしても起きてきてしまう問題が「治そうとされる」という問題なのです。
ここではっきりと述べておこうと思うのですが、私は「植物嫌悪症」を治したいと思ったことは一度もありませんし、治す必要も感じていません。
しかし、私が入れない場所などに遭遇したときに、理由として「植物が苦手です。」とお話しすると、
「認知行動療法を受けてみたら?」
「森田療法を受けてみたら?」
「トラウマ治療を受けてみたら?」
「前世療法を受けてみたら?」
「精神分析を受けてみたら?」
「インナーチャイルド療法を受けてみたら?」
というように、まるで「世界心理療法カタログ」なるものを開いたかのように、ありとあらゆる療法をすすめられるのです。
もちろん、私のせいでその場所に入れなかったり、善意で言っていただいているのがわかるので、むげに断るわけにもいかず、その方のお話しに熱心に聞き入る(ふりをする)のですが、そのたびごとに、お互いの労力を無駄にしている感覚にたいへん疲れ切り、罪悪感も感じてしまいます。
冒頭で、私は自分の植物嫌いを「病気」と呼びましたが、それは、周囲の方々とのあいだにこのようなズレがあるためです。
あくまでも「植物が平気」という多数派から見れば、超数派の私は病気なのだろうという意味であって、私は病気だとは思っていないのです。
また、多数派の人々も「治そう」としてくれるわりには、正式に病気だと認めてはいません。
そのためにカギかっこつきで「病気」と表記しているのです。
私にとっては、植物が気持ち悪く感じる方が正常なのです。
かといって、植物を美しく感じる人を異常だとも思いません。
人それぞれなのだと思うだけなのです。
しかし、そのような感覚は多数派には通じない。
とくに私の「植物嫌悪症」に対しては、よりその傾向が強いように実感しています。
なぜそのような傾向が生まれてしまうのかと言えば、それは世間一般において、植物が「癒し」をもたらす存在として確固たる地位を築いているからでしょう。
つまり、植物を気味悪がるということは、植物に対しての感覚が「ズレている」ていどではなく、「正反対である」ということに、私の「病気」の面倒くささ(悲劇?)があるのです。
ズレているていどであれば、お互いの趣味の違いの延長線上として理解されることもあるでしょう。
しかし、植物嫌悪症の場合は、「癒し」と「おぞましい」という正反対の感覚のぶつかり合いです。
そのために、
「こんなにも誰もが癒されるものを、気味が悪いと思うはずがない」
という驚きが生まれ、それは完全に私の方が異常なのであり、だから治すべきだという感覚にいきついてしまうようなのです。
つまり、「理解されない」をとおりこして「治そう」とされる。
「治そう」とされるだけならまだしも、今後も紹介していきますが、しかられることもあります。
また、植物と話ができるという人(これも結構多い)から、
「あの子たちは、本当にいい子ばかりなの。だからそんなに毛嫌いしないで、優しい気持ちで接してあげてよ。なんでわかってあげようとしないの?なんでかわいがってあげないの?」
と厳しい追及を受けることもあります。
私は、そのような方のもつ能力を否定する考えはありません。
ただ、年功序列がはなはだしい日本文化の中で生まれ育った私には、樹齢千年を超えるものもあるであろう植物をひとくくりにして、
「あの子」
と呼んでしまうフレンドリーさにはついていけず、そのせいか対話はまったく成り立ちません。
また、私の植物への嫌悪感をまったく理解しようとしない人に、「理解してあげて」と頼まれたところで、それは失敗した料理を出されて、
「私は食べないけど、あなたは食べてね」
と言われているような気がして、やはり対話は決裂してしまうのです。
次回も、この「治そうとされる」という問題をもう少し考察してみます。
Brain with Soul代表
生きづらさ専門カウンセラー
しのぶかつのり(信夫克紀)
おかげ様でコラム数500本突破!


 誰もが多数派
誰もが多数派 植物が嫌いという病
植物が嫌いという病 「読むと心が強くなるコラム」一覧
「読むと心が強くなるコラム」一覧